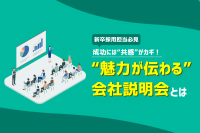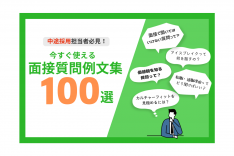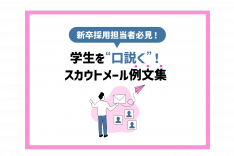PAGE TOP
27卒学生の動向から読み解く、サマーインターン設計のポイント
更新日:2025/05/22

採用競争が激化するなか、サマーインターンシップは“母集団形成の場”にとどまらず、“選考直結の戦略施策”として位置づける企業も増えています。
一方で、「満足度は高いのに本選考に繋がらない」「他社との差別化が難しい」といった声も多く、設計・運営に課題を感じる担当者は少なくありません。
27卒学生の価値観や行動変容を正しく捉え、自社に合った形で魅力づけができるかどうかが、採用成果を左右します。
本記事では、学生ニーズの変化を紐解きながら、サマーインターン設計のポイントを解説します。

社長・経営者と学生がマッチングする理念共感型就職イベント「WinC Audition(ウインクオーディション)」。
相互理解を深めるコンテンツから、共感度の高い学生とマッチングすることができます。
<過去実績>
・1社1回の出展で最高内定受諾数5名!
・最速内定日数はイベント当日から3日!
目次
27卒学生の最新動向
27卒学生の就職活動は、早期化が進んでいます。
株式会社ワンキャリアの調査によると、すでに約半数の学生が2025年1月以前から就職活動を開始しており、春や夏のインターンシップへの動き出しも2〜3月をピークに本格化しています。(※1)
こうしたデータからは、企業選びの初期段階が従来よりも前倒しになっていることがうかがえます。
つまり、企業が学生と接点を持つためには、より早い段階からのアクションが求められるようになっているのです。
しかし一方で、多くの企業が採用を前倒しにしている中で、「早く動けば自然に学生と出会える」という単純な構図はすでに通用しにくくなってきています。
※1:株式会社ワンキャリア 「【27卒】就職活動に関するアンケート」
学生満足度を高める4つの設計ポイント
学び・成長実感が得られるコンテンツ
学生がインターンに求めているのは、単なる業務体験ではなく、自分の成長を実感できる“意味のある挑戦”です。実際のビジネス課題を題材にしたワークや、グループディスカッション、アウトプットに対するフィードバックなど、「考える」「発信する」「振り返る」機会を通じて成長実感を得られる設計が効果的です。特に、結果だけでなくプロセスに目を向けたフィードバックは、学生の納得感や満足度を高め、企業への好印象にも繋がります。
社員とのリアルな交流
若手社員や現場社員との座談会、1on1トークなど、リアルな交流の場を設けることで、仕事内容だけでなく社風や人間関係まで伝わります。
特に、社員が自分のキャリアや入社後のギャップを率直に語る場は、学生の共感を呼び、企業理解の深化に繋がりミスマッチを防止する効果があります。
画一的な説明ではなく、“生きた声”がある場づくりが鍵となります。
自己理解を深められるフィードバック
インターンシップを通じて、学生が得たいことの一つとして挙げられるのが、「自分は何が得意で、どんな場で活躍できそうか」といった自己理解のヒントです。
実際に、ワークやプレゼン後に提供されるフィードバックは、自分自身を客観的に見つめ直す機会として学生にとって重要な意味を持つことがあります。
他社と差がつく魅せ方
優れたプログラム内容があっても、魅力が伝わらなければ学生の心には届きません。学生に向けて、魅力が直感的に伝わる“魅せ方”の工夫が不可欠です。
例えば、参加者の声やインターン当日の雰囲気を動画やSNSで発信するなど、インターンシップ参加前からワクワクさせる仕掛けが有効です。「楽しそう」「他と違う」と思ってもらえる印象づけが、選ばれるきっかけに繋がります。
「満足」だけで終わらせない、選考へのつなげ方
学生にとってインターンが「楽しかった」「印象が良かった」だけで終わってしまっては、本選考へは繋がりません。
大切なのは、インターン中から“その後”を意識した設計を組み込むことです。
例えば、社員との接点を通じてロールモデルを提示したり、企業のビジョンやキャリアパスに触れる時間を設けたりすることで、入社後のイメージが明確になります。また、終了後の個別フィードバックや連絡の継続など、接点を切らさないインターン後のフォローも重要です。学生に「この企業と、もう一歩先の話がしたい」と思わせられる仕掛けが、自然な志望形成と選考参加へと繋がっていきます。
まとめ
27卒学生の就職活動は早期化が進み、インターンシップの目的や期待も多様化しています。
単なる企業理解の場ではなく、「成長機会」や「自己発見のきっかけ」として設計されたインターンこそ、学生の記憶に残り、選考への接続力も高まります。
本記事で紹介した4つのポイントをもとに、学生視点に立ったインターン施策を今一度見直してみてはいかがでしょうか。